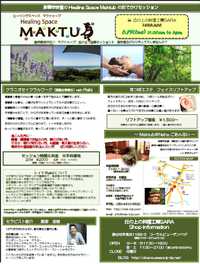2013年06月11日
自分中心か世間中心か…軸の置き方と作られた病、ADHD
ADHDとかADDいう「病」をご存じだろか?
ADHDとは、Attention Deficit / Hyperactivity Disorderの略で、
注意欠陥・多動性障害という行動障害として病気とされている。
ADDはADHDから多動(Hyperactivity)がないもの。
特徴としては、
集中力が続かない
注意力散漫
じっとしていられない
計画性がない
片づけられない
時間の感覚がずれている・時間を守れない
感情的・衝動的…
などなどこれらの特徴が7歳以前から現在まで続いていて、生活に支障をきたしていると
みごと「ADHD認定」が受けられるというものである。
最近は、これらの特徴が病気として定義されたために、
啓蒙活動も行われている。
こないだなんかは、本屋の児童書の売り場で
「ADHDってなに?」的な本が売られているのをみつけて驚いたばかりだった。
そして最近は、Web媒体でもこの手の啓もうをしているようだ。
たとえば…こんな動画がある。
一度見てほしい。
ここまで極端ではないにしろ…
この動画に出てくる彼のような傾向って
誰でももっていそうだよな…とも思わないだろうか?
全部とは言わなくとも、
少しぐらいは片鱗がある人が多いんではないだろうか?
これを書いている僕だって、
思い当たることがたくさんある…どころじゃない。
こういう自分をたくさん知っている。
子供のころはしょっちゅう忘れ物をした。
通学路途中まで行って、引き返したことも多々あるし、
教室で気づいて茫然としたことも片手どころじゃない。
大人になってからだってちょくちょく忘れ物をする。
あんまりかわってない
集中力も続かない
自分の好きなことはすごく集中できるが、
あまり興味がないと話も聞けないし、ぼーっとするし、
興味のあることに気持ちが移りやすくなる。
というかそれ以外どうでもよくなるし、
気が進まないことはとことんできない性分だ。
時間も守るのが苦手だ。それは今もそうだ。
人との約束なんて、遅れていくことのほうが多いぐらい。
学生時代は、レポートの提出期限なんて苦痛でしかなかったし、
サラリーマンやってたときなんかも当然そうだった。
期限だとか納期だとか、数値目標だとか…
目の前のタスクが、自分にとってとても難しく、取り組んだことがないことばかりだったので
おのずと壁が大きく感じられた。
ちょうど彼が、履歴書やエントリーシートを書くのを難しく思うように、
おっくうでナンギなことだった。
でも「できない」は許されないことなんだ
みんな会社勤めをしたらやってることなんだと、自分に言い聞かせて頑張ってみたのだ。
頑張っちゃってたので、僕に、上に書いたような特徴があって、
内部でものすごく葛藤していたことが信じられないという人もいるかもしれない。
しかし、実際は、社会に接し始めたころ(子供時代)から、
自分の中では、ものすごい嵐の日々だった。
おまけにやたら自制心とか理性の強い子だったので、
葛藤を無視して、「あーすべき、こーすべき」と方向付けをし、
持ちこたえられなくなると爆発するという、
今思えば、たいへんおバカなことを大人になるまで繰り返していた。
もちろん、僕が幼いころにはADHDという概念もなかったので、
これらの特徴をそのまま受け容れていいと思っていなかった。
主人公の彼のように、自分を責める日々が続く。
頭の中では、自分に対する叱責ばかりだ。
苦痛に思うのは自分が弱いから、社会に適応できていないから、
と、自分への攻撃を繰り返す。
当然、自分の心の中は穏やかではなく、延々闘いが続くことになる。
闘い続けるのは疲れるので、「そんなのいやだ」「苦痛だ」という面は
そのうち、みないようになってくる。
無感覚を装うとでもいうんだろうか。
しかし解決もしていなければ、認めてもいないので、
見ないふりだけであって、お掃除ができていない状態である。
だから、くすぶりながら普段の生活をごまかしごまかし続けることになる。
会社勤めを辞めて、相当生活のスピードが減速した今だから言えることだけど、
僕には、世の中の時間の流れは速すぎると思うし、
そこに自分を合わせようとしたからつらくなってしまったんだろう。
その場にいて、激動の渦の中にいると、
自分が抑え込んでいるものにも、押さえこんでいること自体にも
なかなか気づけないものなのだ。
今だったら、「自分はそういうの苦手だったんだよなー」と振り返ることができる。
それにADHDという見方もあれば、インディゴチルドレンという言葉にも出会い、
その特徴がADHDやADDに似ているので、自分自身納得できるようになってきた。
そりゃ、仕方ないと思えて腑に落ちているので、もう無理を自分に強いるのはやめている。
「自分のペースがある。」
そう言えるので、正直、どんどん楽になっている。
さて、上に貼りつけた動画の最後なんだが、
「ADHDはそういう特徴があって頑張ってる人たちなんだから、理解してあげてね」
っつー〆になっている。
それをみて、僕はちょっと疑問というか違和感を持った。
「なんだか上から目線だなー」と…。
「自分は正常だと思っている人たち」の目線だなーと…。
以前だったら、そこで思考停止して怒っていたと思う。
怒らずに違和感を探ってみる。
その違和感は、二つのことからきていた。
ひとつは、
どこを主軸にしてとらえるか?で正常と異常を決めているということだ。
これは、動画の作り方も、そして僕自身のとらえ方もである。
さきの「理解してあげてね」は、一般的な社会やそれに適応できる人側の目線で、
主軸は「世の中」にある。
「世の中軸」である。
しかし、一般的な時間のスピード感と違う生き方が心地よい人だっているのも事実だ。
動画の彼のように、僕のように、あるいはどっかの知らない誰かもそうかもしれない。
それは、時間だけじゃない。
たとえば、、、食事。
生活する上で三食食べるのが当たり前となっているが、
三度の食事よりも二食や、あるいはごく少量を何回にも分けて食べるほうが
胃腸の調子がいい人だっているはずだ。
日本はその昔二食の文化だったという話もあるし、階層によって違ってもおかしくない。
宮殿の中にいるような貴族は、肉体を激しく使うわけがないのだから、
腹の減り具合は少なめでもおかしくないし、
農民は肉体労働をするから、三度の飯とおやつが必要だとしても不思議はない(食えたかどうかは別として)
睡眠だって、夜寝たほうがいい人と、明るくなってからのほうが眠れる人、
いろいろいたっておかしくない。
これも出生時間がかかわっている可能性があるという記述をどこかで見たことがある
(…気がする程度なので確定要素ではない。ソースを探してみたけど見つからなかった)
だから、軸を「世の中軸」にしておいて、そこからはずれると「異常」だったり
ちょっとかわいそうテイストをつけられてしまうものなのだ。
個人を軸にとらえることができて、これが自分の快適な生活の仕方だということが理解できたら、
「自分軸」を理解しながら生きることができたら、
自分の中の闘いは減るだろう。
今はちょっと休もう、とか、胃腸がくたびれてるから軽い食事にしようとか…
今夜は眠れないから、眠れないなりの過ごし方をしようとか…
自然で無理をしない生き方に移行していけるだろう。
そしてもうひとつ…
あまりにみんな「世の中軸」に合わせすぎて、「自分軸」を無視するあまりに
他に「自分軸」で生きる人を特別視する傾向が強められているのではないかということだ。
そして自分自身のコンディションはさておいて
「世間一般」とか「標準」「世間並み」というくくりから外れない自分で生きようとしているので、
「自分軸」が認めにくいし、
「自分軸」をもってる人を認めにくくなってしまうということだ。
平ったく言うと「いろんなひとがいてあたりまえ」ではないということ。
「世の中軸」で生きることが当然で、
世の中の大多数の人にそれができているようだと思っていると、
「世の中軸」に合わせられない自分の側面を見つけた場合に、
すんなり「自分軸」と「世の中軸」の差を認めることができるだろうか?
自分のペースにあった選択ができるだろうか?
何らかの理由をつけて「世の中軸」への適応を余儀なくすることが多いのではないだろうか?
「世の中軸」に適応できない「自分軸」の存在が自分の中にあると気づいたら
一体どう反応するだろう?
それじゃいけない
それは自分の勝手だ
それは自分が弱いからいけないのだ
それは社会に適応していないから、自分を矯正しないといけない。。。
それができないと、不適応者、落伍者だと思われる
などと、自分を責めることにならないだろうか?
そういう人ばっかりじゃないかもしれないけど、昔の僕はそうだった。
今だって少しはある(まだたくさんあるかもしれないけどw)
かつての僕以外にもそういう人がいないとも言えない。
自分を責めて、自分にとって楽な生き方が認められず選択できないと、
人は緊張状態を作る。
そして、自分に緊張を強いているので、他の人にもそれを要求するようになる。
甘えてんじゃないとかなんとかかんとか…
それじゃ、この社会で生きていけないとか何とかかんとか…
すくなからずそんな構図はないだろうか?
でもそれは本当だろうか?
本当にやってみたことがあるだろか?
自分の胃袋の具合や睡眠の状態や、
自分のペースとかを探ってみたことがあるだろうか?
それに合わせた実践をしてみたことがあるだろうか?
自分のペースは、頭の中だけで見つかるものではない。
実際にやってみて、「あ、このほうが自分にとって楽♪」という気づきがなければわからない。
肉体ってそういうもんだから…
それに、一発でその方法が見つかるとも限らない。
ちゃんと自分の肉体や心に付き合って、
いろいろ試してみて、やっと腑に落ちるものだと思う。
そんな試行錯誤をしながら、自分軸が素直に受け入れられて、
快適でやりやすい方法を見つけることができれば、
100%とは言わないまでも、徐々に実践していけば、
もちょっと自分を赦すことができて、
自分の中の独自性を認めることにつながるんじゃないかなーとおもうわけだ?
自分がオリジナルな存在だということが分かれば、
他者も同じくオリジナリティがあって、いろんな側面で多様性を受け容れ易くならないかなと思うわけだ。
逆にみんながみんな、自分を「世間並みであること」の縛りを優先し続けていれば
多様性は認めにくくなるということでもある。
この動画は、
一見優しそうだけど、「あなたはあなたでいいんですよ」という話ではないのだ。
これは「病気」と定義づけられているから、
当事者は大変だから支援してあげてくださいね、理解してあげてくださいねだし
最終的に、本人には「精神科にかかって、投薬治療を受けなさい」とかいう雰囲気を醸している。
そしておそらく、「世の中軸に合わせなさい」がオチなんだろうとみることができる。
しかし
しかしだ、まだ続くんだこの話は。
実は、最近このADHDという「病」は、作られた病であることが報じられている。
ADHDは作られた病であることを「ADHDの父」が死ぬ前に認める
『「ADHDの父」と呼ばれるレオン・アイゼンバーグ氏は亡くなる7カ月前のインタビューで
「ADHDは作られた病気の典型的な例である」とドイツのDer Spiegel誌に対してコメントしました。』とある。
ADHDに投薬される「リタリン」という薬に代表されるメチルフェニデートという薬剤は、
アイゼンバーグ氏がADHDの特徴を病気と定義したのち飛躍的にその投薬量が増えているというのだ。
1993年から2011年までの間に約50倍の売れ行きになったという。
(注:日本ではADHDに対して投薬されていない。別の薬剤があるようだ)
病気という定義ができると治療ができる。
誰にでもありがちな特徴を「病気」として宣伝すれば、当事者や親や教育者、それに医師もそれに乗っかりやすくなる。
そうすると処方薬が売れる…
「特徴」=「症状」にしてしまえば、医療ビジネスができるわけだ。
すべてがそうだとは言わないが、こういう側面が多分にあるということは覚えておいたほうがいいだろう。
世の中の経済活動は、そのようにして肥大してきたのだ。
以下リンク先からの引用だが…
『DSM-IVのアレン・フランセス編纂委員長も、DSM-IV発表以降、
米国で注意欠陥障害が3倍に増加したことについて、
「注意欠陥障害は過小評価されていると小児科医、小児精神科医、保護者、教師たちに思い込ませた製薬会社の力と、
それまでは正常と考えられていた多くの子どもが注意欠陥障害と診断されたことによるものです」と指摘。
「米国では、一般的な個性であって病気と見なすべきではない子どもたちが、やたらに過剰診断され、
過剰な薬物治療を受けているのです」と述べています。』
収穫するには、種まきが必要なのだ。
たしかに、病気という定義付け…というか特徴をはっきりさせて「概念化」することによって救われることもある
しかし、それを病気ととらえるか個性ととらえるかによって
対処の仕方もその後の生き方も、さらには社会の在り方も変わるのではないだろうか?
ADHDとは、Attention Deficit / Hyperactivity Disorderの略で、
注意欠陥・多動性障害という行動障害として病気とされている。
ADDはADHDから多動(Hyperactivity)がないもの。
特徴としては、
集中力が続かない
注意力散漫
じっとしていられない
計画性がない
片づけられない
時間の感覚がずれている・時間を守れない
感情的・衝動的…
などなどこれらの特徴が7歳以前から現在まで続いていて、生活に支障をきたしていると
みごと「ADHD認定」が受けられるというものである。
最近は、これらの特徴が病気として定義されたために、
啓蒙活動も行われている。
こないだなんかは、本屋の児童書の売り場で
「ADHDってなに?」的な本が売られているのをみつけて驚いたばかりだった。
そして最近は、Web媒体でもこの手の啓もうをしているようだ。
たとえば…こんな動画がある。
一度見てほしい。
ここまで極端ではないにしろ…
この動画に出てくる彼のような傾向って
誰でももっていそうだよな…とも思わないだろうか?
全部とは言わなくとも、
少しぐらいは片鱗がある人が多いんではないだろうか?
これを書いている僕だって、
思い当たることがたくさんある…どころじゃない。
こういう自分をたくさん知っている。
子供のころはしょっちゅう忘れ物をした。
通学路途中まで行って、引き返したことも多々あるし、
教室で気づいて茫然としたことも片手どころじゃない。
大人になってからだってちょくちょく忘れ物をする。
あんまりかわってない
集中力も続かない
自分の好きなことはすごく集中できるが、
あまり興味がないと話も聞けないし、ぼーっとするし、
興味のあることに気持ちが移りやすくなる。
というかそれ以外どうでもよくなるし、
気が進まないことはとことんできない性分だ。
時間も守るのが苦手だ。それは今もそうだ。
人との約束なんて、遅れていくことのほうが多いぐらい。
学生時代は、レポートの提出期限なんて苦痛でしかなかったし、
サラリーマンやってたときなんかも当然そうだった。
期限だとか納期だとか、数値目標だとか…
目の前のタスクが、自分にとってとても難しく、取り組んだことがないことばかりだったので
おのずと壁が大きく感じられた。
ちょうど彼が、履歴書やエントリーシートを書くのを難しく思うように、
おっくうでナンギなことだった。
でも「できない」は許されないことなんだ
みんな会社勤めをしたらやってることなんだと、自分に言い聞かせて頑張ってみたのだ。
頑張っちゃってたので、僕に、上に書いたような特徴があって、
内部でものすごく葛藤していたことが信じられないという人もいるかもしれない。
しかし、実際は、社会に接し始めたころ(子供時代)から、
自分の中では、ものすごい嵐の日々だった。
おまけにやたら自制心とか理性の強い子だったので、
葛藤を無視して、「あーすべき、こーすべき」と方向付けをし、
持ちこたえられなくなると爆発するという、
今思えば、たいへんおバカなことを大人になるまで繰り返していた。
もちろん、僕が幼いころにはADHDという概念もなかったので、
これらの特徴をそのまま受け容れていいと思っていなかった。
主人公の彼のように、自分を責める日々が続く。
頭の中では、自分に対する叱責ばかりだ。
苦痛に思うのは自分が弱いから、社会に適応できていないから、
と、自分への攻撃を繰り返す。
当然、自分の心の中は穏やかではなく、延々闘いが続くことになる。
闘い続けるのは疲れるので、「そんなのいやだ」「苦痛だ」という面は
そのうち、みないようになってくる。
無感覚を装うとでもいうんだろうか。
しかし解決もしていなければ、認めてもいないので、
見ないふりだけであって、お掃除ができていない状態である。
だから、くすぶりながら普段の生活をごまかしごまかし続けることになる。
会社勤めを辞めて、相当生活のスピードが減速した今だから言えることだけど、
僕には、世の中の時間の流れは速すぎると思うし、
そこに自分を合わせようとしたからつらくなってしまったんだろう。
その場にいて、激動の渦の中にいると、
自分が抑え込んでいるものにも、押さえこんでいること自体にも
なかなか気づけないものなのだ。
今だったら、「自分はそういうの苦手だったんだよなー」と振り返ることができる。
それにADHDという見方もあれば、インディゴチルドレンという言葉にも出会い、
その特徴がADHDやADDに似ているので、自分自身納得できるようになってきた。
そりゃ、仕方ないと思えて腑に落ちているので、もう無理を自分に強いるのはやめている。
「自分のペースがある。」
そう言えるので、正直、どんどん楽になっている。
さて、上に貼りつけた動画の最後なんだが、
「ADHDはそういう特徴があって頑張ってる人たちなんだから、理解してあげてね」
っつー〆になっている。
それをみて、僕はちょっと疑問というか違和感を持った。
「なんだか上から目線だなー」と…。
「自分は正常だと思っている人たち」の目線だなーと…。
以前だったら、そこで思考停止して怒っていたと思う。
怒らずに違和感を探ってみる。
その違和感は、二つのことからきていた。
ひとつは、
どこを主軸にしてとらえるか?で正常と異常を決めているということだ。
これは、動画の作り方も、そして僕自身のとらえ方もである。
さきの「理解してあげてね」は、一般的な社会やそれに適応できる人側の目線で、
主軸は「世の中」にある。
「世の中軸」である。
しかし、一般的な時間のスピード感と違う生き方が心地よい人だっているのも事実だ。
動画の彼のように、僕のように、あるいはどっかの知らない誰かもそうかもしれない。
それは、時間だけじゃない。
たとえば、、、食事。
生活する上で三食食べるのが当たり前となっているが、
三度の食事よりも二食や、あるいはごく少量を何回にも分けて食べるほうが
胃腸の調子がいい人だっているはずだ。
日本はその昔二食の文化だったという話もあるし、階層によって違ってもおかしくない。
宮殿の中にいるような貴族は、肉体を激しく使うわけがないのだから、
腹の減り具合は少なめでもおかしくないし、
農民は肉体労働をするから、三度の飯とおやつが必要だとしても不思議はない(食えたかどうかは別として)
睡眠だって、夜寝たほうがいい人と、明るくなってからのほうが眠れる人、
いろいろいたっておかしくない。
これも出生時間がかかわっている可能性があるという記述をどこかで見たことがある
(…気がする程度なので確定要素ではない。ソースを探してみたけど見つからなかった)
だから、軸を「世の中軸」にしておいて、そこからはずれると「異常」だったり
ちょっとかわいそうテイストをつけられてしまうものなのだ。
個人を軸にとらえることができて、これが自分の快適な生活の仕方だということが理解できたら、
「自分軸」を理解しながら生きることができたら、
自分の中の闘いは減るだろう。
今はちょっと休もう、とか、胃腸がくたびれてるから軽い食事にしようとか…
今夜は眠れないから、眠れないなりの過ごし方をしようとか…
自然で無理をしない生き方に移行していけるだろう。
そしてもうひとつ…
あまりにみんな「世の中軸」に合わせすぎて、「自分軸」を無視するあまりに
他に「自分軸」で生きる人を特別視する傾向が強められているのではないかということだ。
そして自分自身のコンディションはさておいて
「世間一般」とか「標準」「世間並み」というくくりから外れない自分で生きようとしているので、
「自分軸」が認めにくいし、
「自分軸」をもってる人を認めにくくなってしまうということだ。
平ったく言うと「いろんなひとがいてあたりまえ」ではないということ。
「世の中軸」で生きることが当然で、
世の中の大多数の人にそれができているようだと思っていると、
「世の中軸」に合わせられない自分の側面を見つけた場合に、
すんなり「自分軸」と「世の中軸」の差を認めることができるだろうか?
自分のペースにあった選択ができるだろうか?
何らかの理由をつけて「世の中軸」への適応を余儀なくすることが多いのではないだろうか?
「世の中軸」に適応できない「自分軸」の存在が自分の中にあると気づいたら
一体どう反応するだろう?
それじゃいけない
それは自分の勝手だ
それは自分が弱いからいけないのだ
それは社会に適応していないから、自分を矯正しないといけない。。。
それができないと、不適応者、落伍者だと思われる
などと、自分を責めることにならないだろうか?
そういう人ばっかりじゃないかもしれないけど、昔の僕はそうだった。
今だって少しはある(まだたくさんあるかもしれないけどw)
かつての僕以外にもそういう人がいないとも言えない。
自分を責めて、自分にとって楽な生き方が認められず選択できないと、
人は緊張状態を作る。
そして、自分に緊張を強いているので、他の人にもそれを要求するようになる。
甘えてんじゃないとかなんとかかんとか…
それじゃ、この社会で生きていけないとか何とかかんとか…
すくなからずそんな構図はないだろうか?
でもそれは本当だろうか?
本当にやってみたことがあるだろか?
自分の胃袋の具合や睡眠の状態や、
自分のペースとかを探ってみたことがあるだろうか?
それに合わせた実践をしてみたことがあるだろうか?
自分のペースは、頭の中だけで見つかるものではない。
実際にやってみて、「あ、このほうが自分にとって楽♪」という気づきがなければわからない。
肉体ってそういうもんだから…
それに、一発でその方法が見つかるとも限らない。
ちゃんと自分の肉体や心に付き合って、
いろいろ試してみて、やっと腑に落ちるものだと思う。
そんな試行錯誤をしながら、自分軸が素直に受け入れられて、
快適でやりやすい方法を見つけることができれば、
100%とは言わないまでも、徐々に実践していけば、
もちょっと自分を赦すことができて、
自分の中の独自性を認めることにつながるんじゃないかなーとおもうわけだ?
自分がオリジナルな存在だということが分かれば、
他者も同じくオリジナリティがあって、いろんな側面で多様性を受け容れ易くならないかなと思うわけだ。
逆にみんながみんな、自分を「世間並みであること」の縛りを優先し続けていれば
多様性は認めにくくなるということでもある。
この動画は、
一見優しそうだけど、「あなたはあなたでいいんですよ」という話ではないのだ。
これは「病気」と定義づけられているから、
当事者は大変だから支援してあげてくださいね、理解してあげてくださいねだし
最終的に、本人には「精神科にかかって、投薬治療を受けなさい」とかいう雰囲気を醸している。
そしておそらく、「世の中軸に合わせなさい」がオチなんだろうとみることができる。
しかし
しかしだ、まだ続くんだこの話は。
実は、最近このADHDという「病」は、作られた病であることが報じられている。
ADHDは作られた病であることを「ADHDの父」が死ぬ前に認める
『「ADHDの父」と呼ばれるレオン・アイゼンバーグ氏は亡くなる7カ月前のインタビューで
「ADHDは作られた病気の典型的な例である」とドイツのDer Spiegel誌に対してコメントしました。』とある。
ADHDに投薬される「リタリン」という薬に代表されるメチルフェニデートという薬剤は、
アイゼンバーグ氏がADHDの特徴を病気と定義したのち飛躍的にその投薬量が増えているというのだ。
1993年から2011年までの間に約50倍の売れ行きになったという。
(注:日本ではADHDに対して投薬されていない。別の薬剤があるようだ)
病気という定義ができると治療ができる。
誰にでもありがちな特徴を「病気」として宣伝すれば、当事者や親や教育者、それに医師もそれに乗っかりやすくなる。
そうすると処方薬が売れる…
「特徴」=「症状」にしてしまえば、医療ビジネスができるわけだ。
すべてがそうだとは言わないが、こういう側面が多分にあるということは覚えておいたほうがいいだろう。
世の中の経済活動は、そのようにして肥大してきたのだ。
以下リンク先からの引用だが…
『DSM-IVのアレン・フランセス編纂委員長も、DSM-IV発表以降、
米国で注意欠陥障害が3倍に増加したことについて、
「注意欠陥障害は過小評価されていると小児科医、小児精神科医、保護者、教師たちに思い込ませた製薬会社の力と、
それまでは正常と考えられていた多くの子どもが注意欠陥障害と診断されたことによるものです」と指摘。
「米国では、一般的な個性であって病気と見なすべきではない子どもたちが、やたらに過剰診断され、
過剰な薬物治療を受けているのです」と述べています。』
収穫するには、種まきが必要なのだ。
たしかに、病気という定義付け…というか特徴をはっきりさせて「概念化」することによって救われることもある
しかし、それを病気ととらえるか個性ととらえるかによって
対処の仕方もその後の生き方も、さらには社会の在り方も変わるのではないだろうか?
Posted by maktub_J at 08:52│Comments(0)
│つれづれ